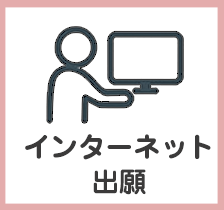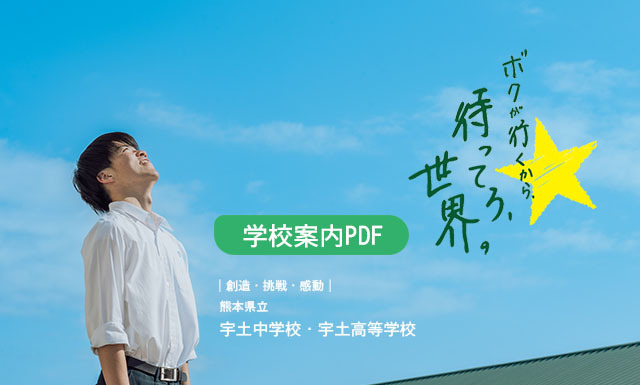学年末を迎え、生徒の皆さんはそれぞれにこれまでを振り返り、これからに思いを巡らしていることでしょう。
本日は、令和7年3月1日に挙行しました宇土高校の卒業式における、小林さんの卒業生総代答辞の全文を掲載します。
不知火やAIの研究で活躍した小林さんですが、学校生活が順風満帆だった訳ではありません。急激に変化する環境に適応できず、中学校時代はほとんど学校に行くことができないこともありました。
今、生徒の皆さんは様々な思いを抱いて学校生活を送っていると思います。新年度の一歩踏み出す勇気につながることを期待して、小林さんのメッセージをお届けします。ぜひ、ご一読ください。
*************************************************
答辞
冬の寒さもようやく和らぎ始め、校舎から見える城山公園にも暖かな春の日差しが降り注ぐ季節となりました。この佳き日に私たち卒業生のために、このような心温まる式典を挙行していただき、卒業生を代表して感謝申し上げます。そして、ご多忙の中、ご出席いただきましたご来賓の皆さま、先生方、保護者の皆さま、そして在校生の皆さんに、卒業生一同、心よりお礼申し上げます。
まず、私が今日、このように卒業を迎えることができたのは、先生方をはじめ、友だちの支えがあったからに他なりません。3年前を振り返ると、私にとって、この卒業式に参加することができたというのは、決して当たり前のことではありませんでした。
中学校時代の私は不登校でした。急激に変わった環境と難しくなった勉強についていくことができず、ほとんど学校に行くことができなくなってしまい、辛い3年間を過ごしました。高校生になったら学校に行けるのか、勉強についていけるのか、不安な気持ちでいっぱいだった私の「高校生活スタートライン」はクラスメイトの皆よりも、ずっと後ろの方にありました。そして、そんな思いをしていたのは私だけではありませんでした。入学式を終えた後、不安そうにしていた両親の顔は今でも覚えています。
しかし、日が進むにつれて、私の心にも少しずつ変化が訪れました。一歩踏み出してみた体育祭。みんなで作品を創り上げる楽しさに気付いた文化祭。先輩がとても偉大に、かつ面白く見えた部活動。おそらくこれは私だけではなかったと思います。高校生活に不安を抱いていた私たちが、この宇土高校というゆりかごの中で、少しずつ小さな羽を伸ばしていき、特に私にとっては探究活動が、自分の不安に打ち勝ち、素晴らしい高校生活を送るきっかけとなっていきました。
この3年間を振り返ると、多くの活動が私たちを大きく成長させてくれました。
体育祭では、毎年何団になるのか、鉢巻が配られるのが楽しみだったのを覚えています。他にも、各自が出場する競技を決めたり、リレーの走順を決めたり、自分の団が勝つために必死で頑張りました。私は毎年綱引きに出場しました。最後尾でアンカーとして綱を全力で引っ張ったのは、いい思い出です。一度綱引きの綱が切れたことがありましたが、それは決して私だけの力ではありません。体育祭終了後、解団式での応援団の姿は印象的でした。リーダーのみんなはとてもかっこ良く、憧れでした。
文化祭では、クラス一丸となって1年生では動画制作を、2年生ではポップコーンや綿菓子を売るバザーをしました。毎日、放課後に教室に残り、みんなで作品を創り上げていくという経験は、あの時の私にとっては、とても刺激的な毎日でした。また、私は部活動の茶道部で、一般の方や宇土中高の生徒の前でお手前を披露しました。あの時のことを思い出すと、今でもドキドキします。
体育祭も文化祭も生徒会の実行委員が、毎日遅くまで走り回っていました。この学校には何かを創り上げるときのエネルギーが充満していると感じています。
そして、私にとって科学部での活動は高校生活での大きな転換点ともなりました。1年生の夏、友だちから不知火現象の観測会に誘われました。軽い気持ちで参加したのですが、一晩中、永尾神社で眠たい目をこすりながら観測を行いました。結局、不知火は見えず、くたくたになりましたが、私の心に灯がともりました。これをきっかけに科学部に入り、先輩方から研究を引き継いで観測や実験を行う中で、不知火に対する情熱がどんどん湧き上がってきました。また、不知火の研究を通してできた友達や、後輩たち、さらには地域の方々とも、貴重な経験を積むことができました。この活動を通して、ともに学び、助け合い、そして喜びを分かち合っていく中で、素晴らしい賞をいただくこともできました。秋の深まる季節、イチョウの木が色づく中、熊本県庁のルフィ像の前で、『県知事賞』を持って写真を撮ったあの記憶は、今でも私に勇気を与えてくれます。今後も、後輩たちが研究を引き継ぎ、宇土高校の新たな伝統にしてくれると信じています。
不登校から立ち直れたのは、宇土高校の先生方や友達など、身近な人たちからの支えがあったからに他なりません。それは、私だけではないと思います。いつも親身になって寄り添っていただいた先生方、また切磋琢磨しあった友達・後輩たち、本当にありがとうございました。そして、いつも温かく私たちのことを陰ながら支えてくれた家族に心から感謝します。これからも私たちの成長をもう少し見守ってください。
卒業を迎える今、私たちはそれぞれの未来に向かって羽ばたこうとしています。近代経済学の父と呼ばれるジョン・メイナード・ケインズは1930年代に、100年後、機械による生産性が大幅に上がり、人間の労働時間が極端に減ると予想しました。実際に、AIはより高度なものとなり、私たちの生活に大きな影響を与えています。VUCAと呼ばれる激動の、先の見えない時代に、私たちはどのような生き方をするべきでしょうか。私は、人間しか持ち得ない創造的な感性を磨くことが重要だと考えます。身近なことに疑問を持ち、あらゆる手法を用いて解決していく力が必要です。小さな疑問(問い)が積み重なれば、大きな課題を解決する糸口になります。
宇土高校では、「自らの課題に誠実に取り組み、諦めずに積み重ねていく」、その土台を作ることができたと思っています。後輩の皆さんも、この「進取敢為」の精神を胸に、何事にも丁寧に、そして全力でこれからの高校生活に向き合っていってください。そして今なら、不安でいっぱいだった入学式のときの私に、「宇土高校なら君を成長させてくれる」と胸を張って言うことができます。
私たちのこれからの道のりには、新たな挑戦が待ち受けています。ときには挫折し、躓くこともあるかもしれません。それでも挑戦することを恐れずに、一歩踏み出す勇気を持って、前に進んでいきたいと思います。ここ宇土高校で学んだことや、支えてくれたすべての人々への感謝を忘れず、これからの人生を歩んでいきます。
最後になりますが、今日まで私たちにたくさんの愛情を注ぎ、応援してくださった全ての方々に心から感謝するとともに、私たちを大きく育んでくれたこの宇土高校のますますの発展を祈念し、答辞といたします。
令和七年三月一日
熊本県立宇土高等学校
第七十七回卒業生総代 小林